「これってハラスメントかも?」
そんなフレーズが頭によぎったり、聞かれる場面が増えた今、私たちは感覚や感情という“境界線のあいまいさ”に向き合わざるを得ない時代にいます。
本記事では、法律や定義では語りきれない「人が不快だと感じる瞬間」に注目しながら、“ハラスメントの正体”と、グレーゾーンに必要な“対話の力”について探っていきます。
ハラスメントとは“法律”ではなく“感情”から始まる
「不快感」がハラスメントの起点
ハラスメントという言葉が使われるとき、私たちはつい「パワハラ」「セクハラ」などの法律上の分類に注目しがちです。
しかし、実際の現場でトラブルになるのは、「どこからどこまでがハラスメントなのか?」「指導や注意となにが違うのか?」という判断の難しい場面。事実と解釈だけでは判断が難しい人の内側に起こったことが原因だからです。
それはつまり、ハラスメントの出発点が“人が不快だと感じたかどうか”という主観的な感情だからなのです。
相手の感情に“意図”は関係ない?
しかし訴えられた側からすると「そんなつもりじゃなかった」「悪気はなかった」「相手にも非がある」と言いたくなることもありますよね。
けれど、相手がすでに“傷ついた”と感じた時点で、すでに関係性にひびを入れた出来事になり、たとえ相手が意図的に訴えることを前提にした行動の結果でも法律上の解決になってしまいます。
そういった事態になる前に、私たちは意図より“伝わり方”を重視して、対話の中で“温度差”を見逃さない力が求められています。
なぜ今、グレーゾーンが問題視されているのか
価値観の多様化と個の尊重
社会の価値観が多様化し、「何を不快と感じるか」が人によってまったく異なる時代。
たとえば「昔は当たり前だった叱り方」「モチベーションのあげ方」が、今では通用しないことも少なくありません。
境界線を“明文化”できない現場のリアル
「これはOK」「これはNG」と明確に線を引きたいと思っても、現実はそう簡単ではありません。
だからこそ、曖昧なゾーン=グレーゾーンにこそ、私たちの“感じる力”と“対話する力”が問われています。
「悪気がない」が通用しない時代の言葉づかい
“言い方”ではなく“伝わり方”がすべて
指導したつもり、励ましたつもり──
でも、相手には「責められた」と受け取られた。そんな経験はありませんか?
言葉の内容よりも、どう伝わったか、そしてその後の関係性にどう影響したかが重要なのです。
語尾に現れる、無意識の力関係
実は、「〜しなさい」「〜でしょ?」など、言葉の最後=語尾には、関係性のパワーバランスが にじみ出ます。
ノン・ハラスメント協会では、語尾マネジメント®という視点から、関係性の改善を図る手法を提案しています。
グレーゾーン時代の対話力とは
「感じ方の違い」を尊重する姿勢
「私は平気だったから、あなたも大丈夫なはず」
この発想が、もっとも危険です。
相手の感じ方は、あなたとは違う。
その前提に立つことで、対話が初めて“対等”になります。
まずは“不快”を“言葉”にしてみる
仕事上、役職が違うのは役割分担の意味があり
そこに上下関係がある職場が大半です。
しかし上下関係があろうと同じ人間であり
コミュニケーションによってお互いに伝えあうことでしか
不快から逃れることはできません。
言われた方は
「それ、ちょっと引っかかりました」
「今の言い方、少し強く聞こえました」
など辞めさせられるかも?といった恐怖や不快を我慢するのではなく、相手を責めずに表現する技術をもっておくのは、これからの時代に必要なスキルです。
また、発言した方も
「どう感じました?」
「強く言いすぎていたら教えて?」
など相手とコミュニケーションを積極的にとる姿勢を言葉にすることが大事です。(家庭でもですが)
ノン・ハラスメントな場づくりに必要なこと
制度よりも、日常の“ふるまい”が空気を変える
マニュアルや通達だけでは、職場の空気は変わりません。
信頼は、毎日の挨拶・声かけ・雑談など、“さりげないふるまい”から育まれていきます。
不快も、快適も、すべては小さなコミュニケーションから始まり、育まれていきます。
「間違い」を恐れずに、言い直せる関係を
誰にでも、間違いはあります。お互いの気持ちを知らないことは、相手が何をかんがえているかわからないという恐怖につながり、我慢がハラスメントへと発展したり、辞めていくことにつながります。
大切なのは、「あのときの言い方、強すぎたかも」と言い直せる空気があること。本音を伝える場をつくれることです。
それこそが、非ハラスメントな文化の土台です。
まとめ:不快というセンサーを、関係の修復につなげる
ハラスメントのグレーゾーンは、「感じ方の違い」が生み出しています。
でも、その違いを“問題”ではなく、“対話のきっかけ”に変えることは可能です。
ノン・ハラスメント協会では、感情に寄り添う対話力を高めるための研修・コンサルティングを提供しています。





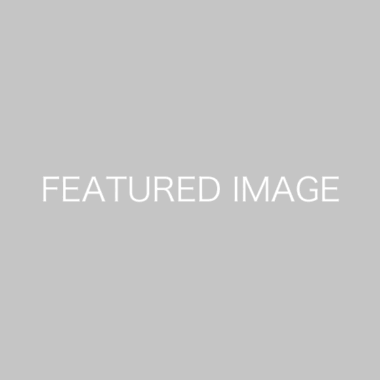







コメント